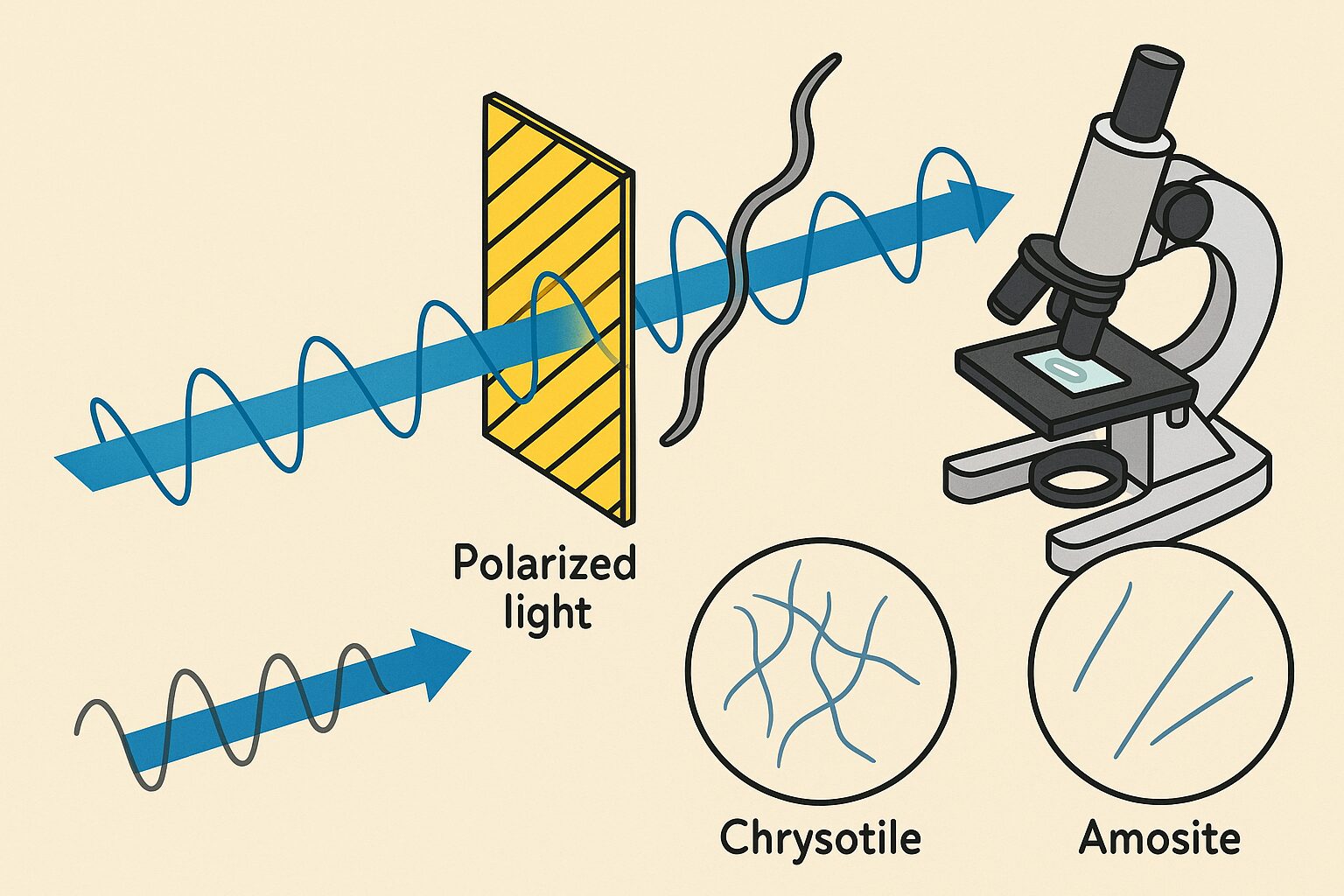(JIS A1481-1準拠)
- 偏光顕微鏡の原理
自然光は進行方向(z軸)にまっすぐ進みますが、同時に電磁波であるため、進行方向と直交するx軸・y軸方向にも振動しながら伝わります。
この自然光を「偏光板」や「鋭敏色板」などのフィルターに通すことで、特定方向に振動が揃った「偏光」を作り出します。
偏光顕微鏡は、この偏光を試料に通し、アスベスト繊維特有の光学的性質を観察する仕組みです。
- アスベスト観察の評価ポイント
JIS A1481-1に基づく偏光顕微鏡分析では、アスベスト繊維の以下の6つの特性を観察します。
- 形態(Morphology)
- 色・多色性(Color & Pleochroism)
- 複屈折(Birefringence)
- 消光特性(Extinction Character)
- 伸長の符号(Sign of Elongation)
- 屈折率(Refractive Index)
これらの組み合わせにより、種類ごとに異なるアスベストを判別可能です。
- 形態の観察(ステップ①)
- 観察条件:光源と試料の間に偏光板を1枚挿入(オープンニコル)
- 観察対象:繊維の形態・長さ・アスペクト比
特徴
- クリソタイル(白石綿)
クネクネと曲がった繊維形態を示す。 - アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、その他角閃石系
比較的直線状の繊維が多い。
JISで定義される「アスベスト様形態」
- 長さ:5µm超
- アスペクト比(長さ/幅):20:1以上
- その他、束状・針状の形態
- 写真例(400倍観察)
- 写真1:クリソタイルの形態(湾曲した繊維)
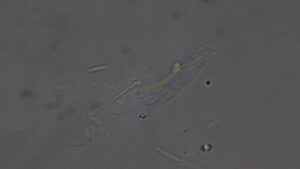
- 写真2:アモサイトの形態(直線的な繊維)